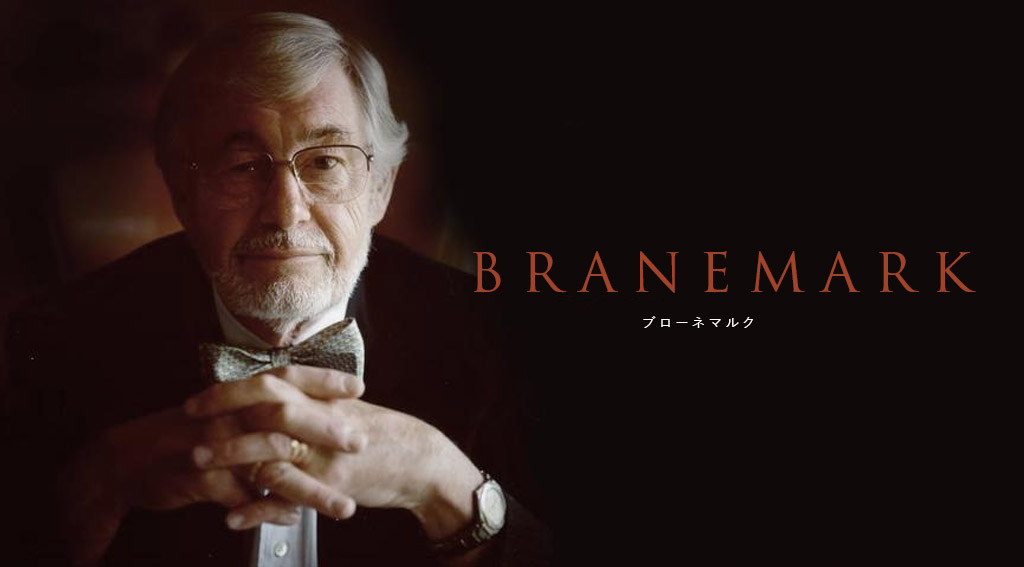
Contents
ブローネマルク氏とは?
ペル・イングヴァール・ブローネマルク(以下、ブローネマルク氏)は1929年5月3日生まれ、2014年12月20日死去のスウェーデンの整形外科医、医学者、歯学者です。デンタルインプラントに革命を起こしたオッセオインテグレーション(骨結合)の発見者であり、世界的に著名なデンタルインプラントシステムであるブローネマルクインプラントシステムの開発者なのです。「現代デンタルインプラントの父」と呼ばれエピテーゼという医療用具として体の表面に取り付ける人工物(※義肢、義眼など)の研究者でもあります。
人物と功績
ブローネマルク氏はスウェーデンのルンド大学医学部で1952年にウサギの脛にチタン製の生体顕微鏡を取り付け微少循環の観察実験を行っていました。その器具を外そうとした際チタンと骨がくっつき外せなくなった事によりチタンと骨の組織が拒否反応を起こさず結合する現象であるオッセオインテグレーションを発見したのです。
その後ヨーテボリ大学に移籍した後も研究を続け、1965年に現在の主流となる世界初の純チタンによるデンタルインプラントシステムの臨床応用を開始しました。最初の患者は先天性歯牙欠損に悩むヨスタ・ラーソンという名前の34歳の男性です。彼は上下顎にデンタルインプラント手術を行い、そのインプラントはその後に彼が亡くなるまでの41年もの期間問題なく機能しています。
1989年にはオッセオインテグレーション技術の普及のためにスウェーデンのヨーテボリにブローネマルク・オッセオインテグレーション・センター(BOC)を設立しました。ブローネマルク・オッセオインテグレーション・センター(BOC)はその後ブラジル、東京など世界9ヵ国に設立され現在に至ります。往年はブラジルサンパウロ州バウルーに在住してデンタルインプラントの治療や指導を行っていました。近年はインプラントを使って固定したエピテーゼという医療用具として体の表面に取り付ける人工物(※義肢、義眼など)の研究も行っており、それに関した著書も多数執筆しています。
なお、それらの業績に対して数多くの賞を受けています。1992年にミニノーベル賞とも呼ばれる、「the Swedish Engineering Academy's equally prestigious medal for technical innovation」を受賞。また、ハーバード歯科医学校よりアメリカ合衆国におけるデンタルインプラントの業績に対し表彰されてヨーロッパと北米で30以上の名誉職に就いていました。息子であるリカードも外科医であり人工関節付きの義足、指の再建等の研究を行っています。
ブローネマルクインプラントシステム
ブローネマルク氏はオッセオインテグレーション(骨結合)発見後には様々な実験を行い歯科治療への応用を探り続け、ついに1965年人間に臨床応用したのです。なぜ歯科医療だったのか?これについては足や腕の骨であれば取り出しにくいため観察できないということもあるでしょうが、口の中の顎骨は体の内と外の境界面でもあるからです。
このオッセオインテグレーション(骨結合)という現象を応用した歯科医療こそが現代でも広く使われているブローネマルクインプラントシステムなのです。ブローネマルク氏が発見したオッセオインテグレーション(骨結合)が無ければ現代におけるインプラント治療は存在しないと言えるでしょう。これこそがブローネマルク氏が「現代デンタルインプラントの父」と呼ばれる所以です。
そして現代医療へ
ブローネマルク氏が発見したオッセオインテグレーション(骨結合)はデンタル・インプラントの分野における画期的なターニングポイントとなっています。以前は金(ゴールド)やコバルトクロム合金などがインプラントの素材として使用されていましたが、ブローネマルクインプラントシステムが確立されて学会に発表されてからというものは、世界のインプラントにはほとんどチタンが使われるようになりました。
歴史的に見た場合にはそれが20世紀後半の出来事である事を考えるとつい最近の事と言えます。オッセオインテグレーション(骨結合)の発見から約半世紀後、手術後すぐに仮歯がセットできるというクイック・インプラント・システムが開発されました
。振り返ってみると1980年代には機能性を重視しており審美的な配慮はされていなかったと言えます。満足な食事が出来ない状態であったものが「噛めるようになった」という事で満足していたからでしょう。しかし1990年代後半になると「噛める」という機能以外にも見た目の美しさである「審美性」も求められるようになりました
。そして骨移植をはじめとする再生治療の進歩が飛躍的にインプラントの技術を向上させる事となります。2000年代には機能的にも審美的にも優れており、最大の課題であったスピード(治療時間や期間)もクリアした画期的な治療方法が確立されました。それがノーベルバイオケア社ポール・マロ博士が開発した「ALL ON 4(オールオン4)」というインプラント治療法です。
これからも歯科医療における技術の進歩は続いていきますが、「現代デンタルインプラントの父」であるブローネマルク氏あっての事です。現代における機能性・審美性に優れ治療スピードも格段に向上した歯科医療の確立にはブローネマルク氏の功績がいかに大きなものであったかがご理解いただけるのではないでしょうか。




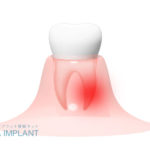




 大分のインプラントなら新港イトセ歯科
大分のインプラントなら新港イトセ歯科






