
健康寿命と歯の関係
近年、高齢化が進む日本ですが、健康に長生きするためには咀嚼する、いわゆる「よく噛むこと」が重要視されています。年齢や治療中の病気や生活習慣などの影響などを除き、歯が多く残っている人や、歯の本数は少なくても義歯などを入れている人の方が、歯が少ない人や、義歯を入れていない人とを比較すると、その後に認知症発症や転倒する危険性が低いということが分かっています。さらに残っている歯が、20本を下回ると咀嚼機能が著しく低下してしまい、適切な栄養を摂取することの障害になる危険性があると、疫学調査の報告でも示されています。
また奥歯1本の噛む力は、人の体重ぐらいの力があるため歯がない状態で噛み合わせが悪かったり、偏った歯に力が長い間かかってしまうと、肩こりや腰痛だけではなく、神経性の病気や内分泌異常などの自覚症状はあるのに、それと体の異常との関係がはっきりしない不定愁訴の原因にもなります。
また、病気の5大疾患である癌、心臓病、脳卒中、肺炎、糖尿病。これらの疾患の原因の一つとして、歯茎の炎症である歯周病も重大な病気として考えられているのです。歯周病になってしまうと、血糖値を下げる働きをするインスリンに体が抵抗するため、効きにくくなってしまい血糖値が上昇します。その結果、糖尿病の発症や糖尿病が進行しやすくなってしまうのです。さらに歯周病になると、歯茎が炎症を起こすため、歯茎が出血しやすくなります。そのため、歯茎の毛細血管が傷ついてしまい血管を通じて血液によって歯周病菌が全身に運ばれ、動脈硬化や心筋梗塞などの心臓病の原因になると考えられています。また、高齢の方にとって肺炎は深刻な疾患の一つです。日本人全体の肺炎による死因の割合は約10%ですが、そのうちの9割が65歳以上の高齢者なのです。高齢になると飲み込む力が低下してしまうため、誤嚥性肺炎が原因で亡くなる人が多いのです。歯の健康と共に、口腔の機能も維持することで、誤嚥性肺炎を起こしにくくなると言われており、健康寿命を延ばすことにもつながるのです。きる問題
今後、日本でますます課題になると言われいる認知症。この認知症も歯と関係しているのです。健康な歯が多く、虫歯になっても治療している人や、歯が残っているという人は、認知症になりにくいと分かってきたのです。歯で食べ物を噛み砕く際、その振動は脳に直接伝わります。さらに、歯根膜から神経を経由して神経伝達物質が脳に伝わり、それらが刺激となるため、脳の血流量が増加して脳の働きが活性化されます。しかし歯の本数が減ってしまい、噛む回数が減ってしまうと歯から脳への刺激も減ってしまい、脳は次第に委縮し退化してしまいます。
さらに近年では、硬い食べ物よりも、柔らかくて食べやすいものをよく食べるようになった事が原因で、現代人は歯や顎の強さが低下しています。よく噛んで食べるという事は大切だと昔からよく言われていますが、消化を助ける以外にも、脳への刺激を増やすという効果があるのです。そのため、歯が健康な状態であれば適度に硬いものを普段から意識して食べることをお勧め致します。 また、歯がない状態では、その分だけ歯から脳への刺激が減ってしまいます。歯を1本失うごとに認知症になる確率は増え、最終的に自分の歯が全くない状態なってしまうと認知症の確率は約2倍になります。しかしインプラント治療や入れ歯などで歯を取り戻すことにより、脳に刺激が伝わる状態に戻ることができます。特にインプラント治療の場合は、神経は抜いているため神経伝達はできませんが、顎の骨と結合しているため、衝撃と振動が脳にしっかりと伝わることができます。
歯周病を予防するために
歯周病菌や虫歯菌は人から人へ感染します。ですので家族みんなでお口を清潔に保ち、感染の時期を遅らせる事が大切なのです。そのためには、正しい歯ブラシ磨き方以外にも、歯間ブラシやフロスを使用して、歯ブラシでは届かない歯と歯の小さな隙き間などは、虫歯や歯周病になりやすいのでしっかりと磨きましょう。 しかし、日々の食事での食べ残しなどは一生懸命に歯磨きしても全てはなかなか取り除くことができません。磨き残しなどは歯垢(プラーク)として歯茎や歯周ポケットに残り、溜まってしまいます。歯垢はやがて硬い歯石へと変化してしまいます。 ご自身の歯磨きで落とせる歯垢と違い、歯石はご自身では取るのが非常に難しいため、歯科医院でのスケーリングやPMCTにより徹底的にバイオフィルム(歯周病菌などの微生物の集合体)を取り除きます。
バイオフィルムを取り除くと菌は除菌されます。バイオフィルムは1週間ほどで再形成されますが、ご自身での正しいお手入れをしっかり行うことで、約3ヶ月間は細菌の活性を抑えることができます。
健康寿命と歯の関係の大切さ
現在の日本は、歯がなかったり、うまく噛むことができない高齢者が増加しています。よく噛むことで顎の骨の振動により刺激が脳や耳に伝わり、記憶や視力に影響するので、老化を遅らせることもできます。またゆっくり噛むことで満腹中枢が刺激され食事量が減少するので体脂肪が分解され、ダイエットや肥満の予防にもなり、さらに唾液の分泌の促進されるため、活性酸素を抑制する結果、アンチエイジングや美容効果、更には癌の予防にも繋がります。
このように健康寿命と歯には、とても密接な繋がりがあるのです。毎日を健康に生活するためにも、ご自身でのお手入れ、そして定期的に大分県の歯科医院で、ご自身の現在の歯の状態をチェックして頂くことをお勧め致します。


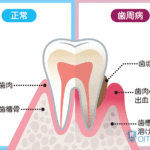







 大分のインプラントなら新港イトセ歯科
大分のインプラントなら新港イトセ歯科






