
虫歯や歯周病は進行してしまうと歯を失ってしまう大きな原因です。そのほかにも歯を失う原因の一つとして、酸性度が強い柑橘類や酢、炭酸飲料などを食べたり飲んだりすると、酸によって歯が溶け出してしまう酸蝕歯があります。歯の表面のエナメル質からリン酸カルシウムの結晶が溶け出してしまうのです(脱灰)。このように酸蝕歯になってしまう症状を酸蝕症といいます。さらにエナメル質は、酸性度がpH5.5以下のものに対して弱く、酸性の飲食物ばかりを取っていると脱灰が起こってしまい、酸蝕症を引き起こすのです。酸蝕歯はの特徴は、冷たいものや熱いものが歯にしみたり、歯の角が丸みを帯びて見えるたり、歯の表面につやが無くなったり、歯の表面に小さなへこみが見られたり、詰め物や被せ物が外れやすくなるなどと様々です。
以前は、メッキ工場やガラス工場などの塩酸、硫酸、硝酸を取り扱う場所で酸性ガスやミストを吸ってしまうことで、酸蝕症を引き起こす職業病と考えられていましたが、現在は飲み物や食べ物が酸蝕歯になる外部からの主な原因であると言われています。
しかし飲食物以外でも体の内部からの原因によって酸蝕歯になってしまうことがあるのです。
体の内部が原因(内因性)で引き起こる酸蝕歯
飲み物や食べ物以外にも、酸蝕症を引き起こすものがあります。それは胃液から出る胃酸です。胃酸はpH値が1.0~2.0と、とても強力な酸で、これが口の中に流れ込むことによって酸蝕症を引き起こす大きな原因となります。逆流性食道炎などによる胃酸の逆流や、拒食症などの摂食障害やアルコール中毒などによって嘔吐などをした場合が続いてしまうと、口の中が酸性寄りになってしまい酸蝕歯になりやすくなります。胃酸の逆流を起こす原因は加齢も関係しています。加齢とともに下部食道括約筋は弱くなるため、過食や脂分の多い食事や深夜の食事などは、寝ている間に胃酸が逆流する原因となります。さらに睡眠時は唾液の分泌が少ないため、胃酸を中和できず酸蝕歯になる危険性があります。
歯磨きに注意
酸蝕症を引き起こしている場合の歯磨きは注意が必要です。酸が歯に接触すると、硬いエナメル質の表面は一時的に軟らかくなります。そのため歯やハブラシが触れただけでもエナメル質がダメージを受けやすくなります。そのため力を入れすぎたブラッシングは、食べ物や飲み物に含まれる酸によるエナメル質へのダメージを大きくしてしまいます。そのため歯磨きの際は、歯質を強化するフッ素などの成分が含まれている歯磨き剤を使いましょう。
またご自身でのセルフケアだけではなく、大分県のかかりつけの歯科医院で治療をするようにしましょう。治療では歯質を守る薬剤を歯に塗って固め、歯を保護する治療をおこないます。また歯に穴が空いていたり欠けていたりと、歯への影響が大きい場合は、詰め物や被せ物をする処置をおこないます。
酸蝕歯の予防法
近年、若年の清涼飲料水の摂取量の増加や、拒食症などの摂食障害による自発的な嘔吐、健康志向に伴った酢やクエン酸やワインの摂取量の増加、高齢者が増加することによって胃食道逆流症も増加したことにより酸蝕症が急増しています。酸蝕歯にならないためにも、酸性度の高い飲食物を摂りすぎないようにすることや、酸性度の高い飲食物を摂った後はうがいをし直後には歯磨きをしない、などといった食生活の見直しや食後のセルフケアが大切です。また流性食道炎などの疾患のある方は原因となっている疾患が治癒することが重要です。また、就寝中は唾液の分泌が少なくなるため中和しにくくなります。さらに、いびきをかく癖がある方は口が乾きやすくなるため、口の中が酸性の状態のままになりやすくなってしまいますので、就寝前は酸性度の高い飲食物を控えるようにしましょう。


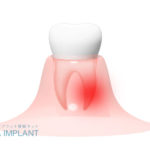






 大分のインプラントなら新港イトセ歯科
大分のインプラントなら新港イトセ歯科






