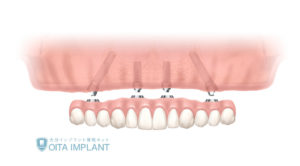まだ歯が生えていない場合や、歯が生え始めたばかりの赤ちゃんは歯みがきをした方が良いのか分からない保護者の方も多くいらっしゃると思います。また、1日に何回磨くのが良いのかという回数も分からないかもしれません。実はこの頃からの歯のケアによって、歯みがきを好きになるか嫌いになるかが決まってしまう可能性があるのです。
Contents
乳幼児の歯磨き
乳歯が生える前から口腔内を清潔に保ちましょう
歯磨きの習慣をつけるのは、乳歯が生えてきてからでも良いですが、歯がまだ生えていないうちから口腔内をキレイにすることに慣れさせておくことは大切です。授乳やミルクを飲ませた後に、保護者の指にガーゼを巻いて口腔内をやさしく拭ってあげます。こうすることで、口腔内の異物感に早い段階で慣れておくと、歯磨きが必要となった際に抵抗なく移行しやすくなります。
ガーゼ磨きをしましょう
歯が生え始めた頃の赤ちゃんは、大人と比べて唾液の分泌量が多いため自浄作用が高く、ガーゼ磨きだけでも十分にキレイになります。また、歯ブラシよりも柔らかな素材のガーゼを使うことは、赤ちゃんにストレスを感じさせることなく歯を磨くことができるため効果的です。ガーゼ磨きは、使いやすいサイズにカットした綿100%の清潔なガーゼをぬるま湯で湿らしせてから、人差し指に巻きつけて赤ちゃんの歯の裏と表を優しく拭きます。これを授乳や離乳食後、就寝前など、1日5〜6回を目安におこない口腔内を清潔に保つようにしましょう。
ガーゼ磨きのコツは、赤ちゃんがリラックスできるように、しっかりと抱っこした姿勢でおこないましょう。お風呂の後に髪や体を拭く流れでガーゼ磨きをするのも良いです。また、赤ちゃんの上唇の裏側と前歯の間には「小帯」というヒダがあるので、傷つけないように指先の力を抜いて、そっと優しく歯をつまむように拭きましょう。もしも赤ちゃんがガーゼ磨きを嫌がったり、泣き出した場合は無理に続けなくても大丈夫です。落ち着くまで少し時間を置いてから再度おこないましょう。最後まで機嫌よくガーゼ磨きができた時にはたっぷり褒めてあげることも大切です。
慣れてきたら歯ブラシで磨きましょう
口腔内を触られることに慣れてきたら、歯ブラシを使って磨きましょう。歯磨きの際は、乳児用の小さな歯ブラシで、歯に触れる程度から始めてみましょう。いきなり歯ブラシで汚れを落とそうとせず、歯ブラシの刺激に慣れさせる期間も大切です。最終的に、1本の歯を5秒ほど優しく磨くことができれば十分です。
歯磨きの回数と時間
大人は違い、歯磨きを始めたばかりの赤ちゃんは1日1回でもきちんと歯磨きができれば大丈夫です。むやみに回数を増やすことよりも、丁寧に磨いてあげることが大切なのです。その場合、磨くタイミングは就寝前がお勧めです。虫歯菌である「ミュータンス菌」は、唾液の分泌量が少なくなる寝ている間に繁殖しやすいため、寝る前にしっかりと歯を磨きましょう。歯みがきに慣れてきて1日2回磨けるようになってきたら、夜寝る前に加えて朝食後におこなうことが理想的です。また、上の前歯の歯と歯の間や、歯と歯茎の間は磨き残しが多くなりがちなので注意して磨くようにしましょう。
乳幼児の歯の磨き方
・歯ブラシの持ち方と力加減
歯ブラシを、鉛筆を持つように持つ「ペングリップ」だと、余計な力がかからずに歯ブラシをコントロールしやすくなります。ブラッシングの力加減は、軽く毛先が広がるくらいのが良いです。歯ブラシの毛先を5〜10mmを目安に小刻みに移動させるようにして磨きます。
乳歯の磨き方
乳歯が1〜2本のうちは、ブラシ部分を1本の歯全体に被せて、そっと回転させながら磨きましょう。歯の本数が増えてきたら、歯の表面に直角になるようにブラシを当てて、全体を満遍なく磨きましょう。立体的な奥歯は、上の面や歯の周囲、裏側も忘れずに丁寧に磨いて、磨き残しがないように気を付けて磨きましょう。
両手で赤ちゃんの顎を固定しながら磨く
下の歯を磨く時は、歯ブラシを持つ手の小指と薬指を赤ちゃんの顎に沿わせて固定させ、もう片方の手で頬を支えると安定して磨くことができます。上の歯を磨く時は、歯ブラシを持つ手を赤ちゃんの頬に沿わせ、もう片方の人差し指で赤ちゃんの上唇の奥にある小帯を守りながら磨くようにしましょう。
仕上げ磨きをおこないましょう
母乳や離乳食などを磨き残してしまうことで、乳歯が虫歯になってしまうこともあります。そのため、乳歯の磨き残しを防いで虫歯をしっかりと予防することが大切です。赤ちゃんの間はもちろん、1人で磨けるようになってからも9歳くらいまでは、保護者の方が仕上げ磨きをしてあげましょう。




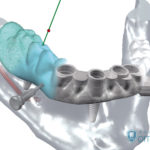


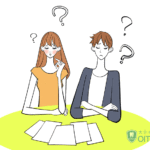

 大分のインプラントなら新港イトセ歯科
大分のインプラントなら新港イトセ歯科